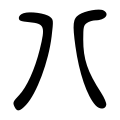八部
| 八 | ||||||||||||||
| 康熙字典 214 部首 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入部 | 八部 | 冂部 | ||||||||||||
| 1 | 一 | 丨 | 丶 | 丿 | 乙 | 亅 | 2 | 二 | 亠 | 人 | 儿 | 入 | 八 | 冂 |
| 冖 | 冫 | 几 | 凵 | 刀 | 力 | 勹 | 匕 | 匚 | 匸 | 十 | 卜 | 卩 | 厂 | 厶 |
| 又 | 3 | 口 | 囗 | 土 | 士 | 夂 | 夊 | 夕 | 大 | 女 | 子 | 宀 | 寸 | 小 |
| 尢 | 尸 | 屮 | 山 | 巛 | 工 | 己 | 巾 | 干 | 幺 | 广 | 廴 | 廾 | 弋 | 弓 |
| 彐 | 彡 | 彳 | 4 | 心 | 戈 | 戶 | 手 | 支 | 攴 | 文 | 斗 | 斤 | 方 | 无 |
| 日 | 曰 | 月 | 木 | 欠 | 止 | 歹 | 殳 | 毋 | 比 | 毛 | 氏 | 气 | 水 | 火 |
| 爪 | 父 | 爻 | 爿 | 片 | 牙 | 牛 | 犬 | 5 | 玄 | 玉 | 瓜 | 瓦 | 甘 | 生 |
| 用 | 田 | 疋 | 疒 | 癶 | 白 | 皮 | 皿 | 目 | 矛 | 矢 | 石 | 示 | 禸 | 禾 |
| 穴 | 立 | 6 | 竹 | 米 | 糸 | 缶 | 网 | 羊 | 羽 | 老 | 而 | 耒 | 耳 | 聿 |
| 肉 | 臣 | 自 | 至 | 臼 | 舌 | 舛 | 舟 | 艮 | 色 | 艸 | 虍 | 虫 | 血 | 行 |
| 衣 | 襾 | 7 | 見 | 角 | 言 | 谷 | 豆 | 豕 | 豸 | 貝 | 赤 | 走 | 足 | 身 |
| 車 | 辛 | 辰 | 辵 | 邑 | 酉 | 釆 | 里 | 8 | 金 | 長 | 門 | 阜 | 隶 | 隹 |
| 雨 | 靑 | 非 | 9 | 面 | 革 | 韋 | 韭 | 音 | 頁 | 風 | 飛 | 食 | 首 | 香 |
| 10 | 馬 | 骨 | 高 | 髟 | 鬥 | 鬯 | 鬲 | 鬼 | 11 | 魚 | 鳥 | 鹵 | 鹿 | 麥 |
| 麻 | 12 | 黃 | 黍 | 黑 | 黹 | 13 | 黽 | 鼎 | 鼓 | 鼠 | 14 | 鼻 | 齊 | 15 |
| 齒 | 16 | 龍 | 龜 | 17 | 龠 | |||||||||
康熙字典214部首では12番目に置かれる(2画の6番目)。
概要

「八」は人が別れて背き合う姿に象るといわれ、「分かれる」の意味を表す。数字の8の意味は後に仮借によって生じた。
偏旁として使われるときは多く冠の位置に置かれる。その場合、「兼」のように上が広く下が狭い形に変化することもある。
八部は「八」を構成要素とする漢字を収めるとともに、「八」の字形を筆画として持つ漢字も収める。そのうちで多いものに「共」や「兵」のように脚の位置で「一」の筆画の下に「八」があるものがあるが、これは「廾」(キョウ)の変形であり、「両手でささげる」意味を表す。
書体によっては右側の払いの上部に横棒(屋根または筆押さえとも呼ばれる)が付くことがある。これは通常デザイン差とされるが、辞書によってはこれがあるものが旧字体、無いものが新字体としているものもある。
数字では二以外の四、六、八の偶数で使われており、2等分できる数字として使われている。
片仮名の「ハ」はほぼ同じ形をしているが、それは漢字の「八」から造られたからである。
部首の通称
八
- 日本:はち、はちがしら、は
- 中国:八字頭、八字底
- 韓国:여덟팔부(yeodeol pal bu、やっつの八部)
- 英米:Radical Eight
部首字
八
-
 甲骨文
甲骨文 -
 金文
金文 -
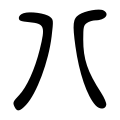 大篆
大篆 -
 小篆
小篆
例字
八部の画数が最大である漢字
𠔻(読み方は「せい」)。